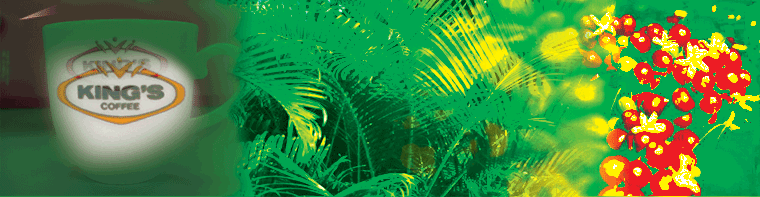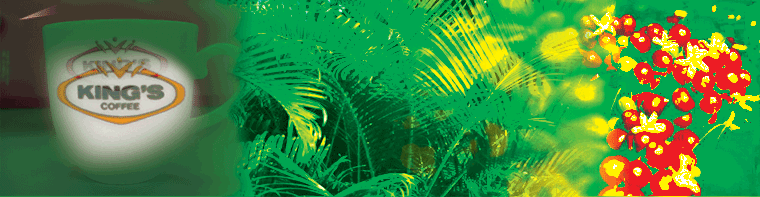歴史の道・竹田
REKISInoMITI・TAKETA

2019年7月
「豊後路・竹田」
BUNGOJI・TAKETA
「人間広瀬武夫中佐論」
「原発と原発事故を考える」
「世界平和のために」
を掲載しています。
内容にご意見があればご連絡ください。
|
| Information |
■HOME>>7月15日更新しました。New
■歴史の道/豊後路・竹田>>豊後路・竹田
■竹田の名所旧跡・食べ物>>竹田の見所
■広瀬武夫の話>>広瀬武夫の話(人間広瀬武夫中佐論)
■広瀬武夫年表 >>広瀬武夫年表:
■田能村竹田の話>>田能村竹田の話
■滝廉太郎の話>>滝廉太郎の話
■世界平和のために
■コラム1.なぜ豊後路・竹田か
■コラム2.竹田というところ
■コラム3.カボスの話
カボスの収穫は通常8月下旬頃から10月末頃です。
我が家のカボスの木に花が咲き、今、2つですが小さい実をつけています。(2019年6月6日)
■コラム4.広瀬武夫の話
■コラム5.珈琲の話>>衛藤六蔵と珈琲
■コラム6.カッピング・ジャッジの話
■コラム7.原発問題を考える
■コラム8.秘密保護法案について
■コラム9.集団的自衛権を考える・・・世界平和実現のために・・・
■コラム10.憲法の解釈について
■コラム11.安保法案強行採決について
■Colum12.参院でも安保法案強行採決(2015.09.28.)
|
| Column1.なぜ豊後路・竹田か |
なぜ豊後路・竹田か?私のお墓が竹田にあるからである。私は小さい頃から学校が休みの時には竹田に良く遊びに行った。これまでに30回近く行っただろうか。父・衛藤六蔵は竹田の出身で、当時、竹田には父の兄弟が居た。寺町の御客屋敷には佐藤次比古が住んでいた。遊びに行くと伯父・次比古に屋敷の拭き掃除と風呂焚きを日課としてさせられたのを思い出す。また、下木には加藤八千代が住んでいた。加藤八千代はお茶の先生をしていた。伯母・八千代からはお茶と竹田の料理をいろいろとご馳走になった。今になると、お茶を習っておけばと思う。最近は、竹田にいくと阿南福登先生ご夫妻にお会いし、話をするのが楽しみになっている。阿南さんには竹田と竹田料理についても教えていただいている。
|
| Column2.竹田というところ |
竹田というところ
竹田は九州のほぼ中央にあり、大分県に属している。さらに言えば、大分県の南西部にあり、阿蘇外輪山の東側に位置している。交通の要衝の地である。昔は豊後の国・竹田と呼ばれていた。竹田は古くからの城下町で文人・墨客の集う文化都市としても栄えたところ。岡藩の初代「中川秀成」(在位1593〜1612)によって区画整理された。また竹田には「歴史の道」という道がある。「歴史の道」をた歩くと、竹田の良さがわかる。「歴史の道」という言葉はだれが考えたのだろうか?竹田にふさわしい良い言葉だと思います。
竹田の由来
気になっていることがある。その一は「竹田とはどういう意味か?」ということ。竹が群生しているところという意味だろうか?竹田(たけた)というと豊後の竹田ではなく、子守唄の京都の竹田と思う人が多い。両者は場所と発音が異なる。豊後の竹田は「たけた」と発音する。京都の竹田は「たけだ」と発音する。
その二は竹田はいつから竹田と言われるようになったのか?ということ。一説によると、竹田と言われるようになったのは緒方三郎惟栄(これよし)が現在の岡城址に保塁を築いた頃(1000〜1200年)らしい。
参考文献:
1.歴史の道 作者?
2.采薇堂二集 後藤均平 草風館
| Column3.カボスの話 2011.10.14. |
竹田特産のカボスは9月から10月が旬です。
(収穫時期は8月下旬から10月の間)
カボスはスダチより香り・酸味は弱いが、上品で柔らかく、まろやかな酸味があり、刺身、白菜の漬物によく合う。ポン酢の酢として使うと最高のポン酢になる。
1. カボスとは
(1)名称・語源
分類:ミカン科ミカン属カボス種
学名:Citrus sphaerocarpa、和名:カボス
愛称:森のサファイア(見城みえ子)
語源:カボスの皮をきざんで「蚊いぶし」に使われたところから、「カイブシ―カブシ―カブス―カボス」になったといわれている。大分県の 一部ではいまでも「カブス」が使われている。
(2)概要・特徴
カボスはミカン科ミカン属の常緑樹で、柑橘類の一つ。ユズの仲間(近縁種)である。これらは酸味が強く、食べるには適さず 、香りを楽しむ柑橘類なので、とくに「香酸柑橘」という。
カボスはミカン・ユズ・スダチとは異なる独特の香りと酸味を有している。ミカン・ユズ・スダチとの違いについては後述(6.)する。
(3)成分
主成分はクエン酸と言われているが、詳細な成分分析が必要である。
2.カボスの歴史
カボスはいつ、どこで誕生したか?江戸時代から栽培されている。元禄八年(1702年)、徳川綱吉の時代、医師宗玄によって京都より大分の地にもたらされたと伝えられている。苗木の発祥の地は中国で、古来正月食の飾り付けとされた。また高血圧療法の薬として親しまれ、家庭で食欲増進のため食卓に出すようになった。
3.カボスの産地
大分県とくに竹田市を代表する特産品である。
収穫時期は8月下旬から10月である。
4.カボスの使い方・利用
刺身・焼き魚・焼き肉などの薬味、なべ料理のポン酢、酢の物など。
5.カボスの加工
ジュース、菓子・ 酒類等の加工品など。
6.ミカン・ユズ・スダチとの違い
(1)ミカン
ミカン科ミカン亜科ミカン属ミカン区に属する柑橘の総称。
一般的に親しまれているのはウンシュウミカン。
ウンシュウミカンは日本原産。
田中長三郎によると、江戸初期の1927年に中国・セッコウ省の黄岩から現在の鹿児島県出水郡長 島地方にもたらされた「早きつ」または「慢きつ」の偶発実生とされている。
(2)ユズ
中国(中央および西域、揚子江上流)が原産で、日本には飛鳥・奈良時代に伝来していた。
飛鳥・奈良時代に栽培していたという記載がある。
本来、12月が最盛期、青ユズは初夏、黄ユズは秋。
ホンユズ。柑橘類のなかでは耐寒性が強く、極東で自生できる数少ない種。
日本では東北以南で広く栽培されている常緑小高木。無農薬栽培ができる。
(3)スダチ
徳島県を代表する特産物。主な産地は徳島県神山町や佐那河内村。大阪方面 面で多く使用され ている。
(竹田の見所にも掲載。)
なお、
竹田特産のカボスはホームページ:http://www.nobiruen.sakura.ne.jp/kabosu.htmlでご注文できます。
|
|
| Column4.広瀬武雄の話 2010.10.27. |
「おう鳴フォーラムin竹田:広瀬武雄」に参加して。
広瀬武夫とは日露戦争の旅順港閉塞作戦で戦死した広瀬武夫中佐のこと。昨年、坂の上の雲に登場したこともあり、見直されている。私は父・六蔵が広瀬武夫と従兄弟同士ということもあり、関心を持って見ています。10月23日に武夫の誕生の地である竹田でおう鳴フォーラムin竹田「時代の開拓者:広瀬武夫」が開かれました。
歴史資料館前には新しい広瀬武雄像(辻畑隆子氏作)も立てられました。大勢の参加がありました。私もその一人です。
「おう鳴フォーラムin竹田:広瀬武雄」は出席する価値のあるフォーラムでした。大勢の人があつまり、講演もみな素晴らしいものでしたし、いろいろな方と交流を深めることができました。その中に、ロシア連邦大使館一等書記官のフェシュン氏の「この地球で戦争を繰り返さないこと」という言葉がありましたが、私が書いた小論文「世界平和実現のために」の内容と、偶然ですが同じのものでした.。
なお、私が書いた小論文「世界平和実現のために」はこのホームページの「広瀬武夫の話」に掲載しています。 衛藤正徳(記) |

広瀬武雄像
辻畑隆子氏作
歴史資料館前
|
| Column5.珈琲の話 |
衛藤六蔵と珈琲
衛藤六蔵は1903年に大分県竹田に生まれ、1928年に渡伯し、ブラジルで5年間生活した。その間、サントス珈琲取引所で2年間珈琲について学び、珈琲鑑定士の資格を授与された。1934年に帰国し、以後日本で珈琲の普及に努めた。詳しくは六蔵物語をご覧下さい。>>http://www.kingscoffee.com/
 |
1930年頃のサントス珈琲取引所。
この頃は実際に珈琲の鑑定をし、格付けを行っていた。
(衛藤六蔵撮影) |
 |
2005年の旧サントス珈琲取引所。
珈琲博物館になっている。
(衛藤正徳撮影) |
|
| Column6.カッピング・ジャッジの話 |
カッピング ジャッジ(Cupping Judge)は、
1.医学では吸角法のこと。
2.珈琲では、珈琲鑑定における重用な作業で、抽出したコーヒーを吸い込み、口に含み、その香味を判定(鑑定)し、ランク付けをすること、あるいはするもの。ブラジルとSCAAのカッピング ジャッジが有名。
SCAAのカッピング ジャッジは正式にはSCAA公認カッピング・ジャッジ(SCAA Certified Cupping Judge)という.。SCAAはスペシャルティ・コーヒー・アソシエイション・オブ・アメリカ(全米スペシャルティ・コーヒー協会)のこと。またカッピング・ジャッジは珈琲鑑定士のこと。
ちなみに、私(衛藤正徳)は2006年にSCAA公認カッピング・ジャッジの資格を得ています。父・六蔵がブラジルの珈琲鑑定士の資格をえているので、親子2代にわたって得たことになる。
|
|